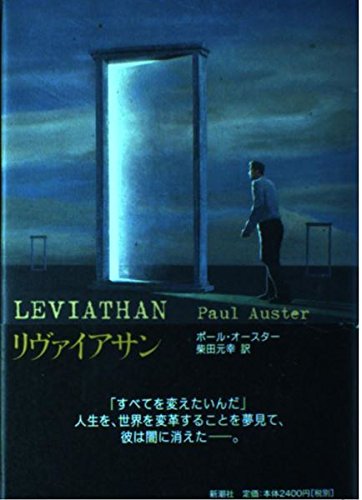1、作品の概要
1951年7月15日に朝日新聞社より刊行された。
朝日新聞の1950年12月12日号~1951年3月31日号で、全109回に亘って連載された。
1951年8月に映画化された。
監督は成瀬巳喜男。
後期の作品群で、重要なテーマになった『魔界』が初めてテーマとして出てきた作品。
かつてのバレエのプリマドンナだった波子と、その娘の品子を中心に4人家族の危うい関係性を描いた。
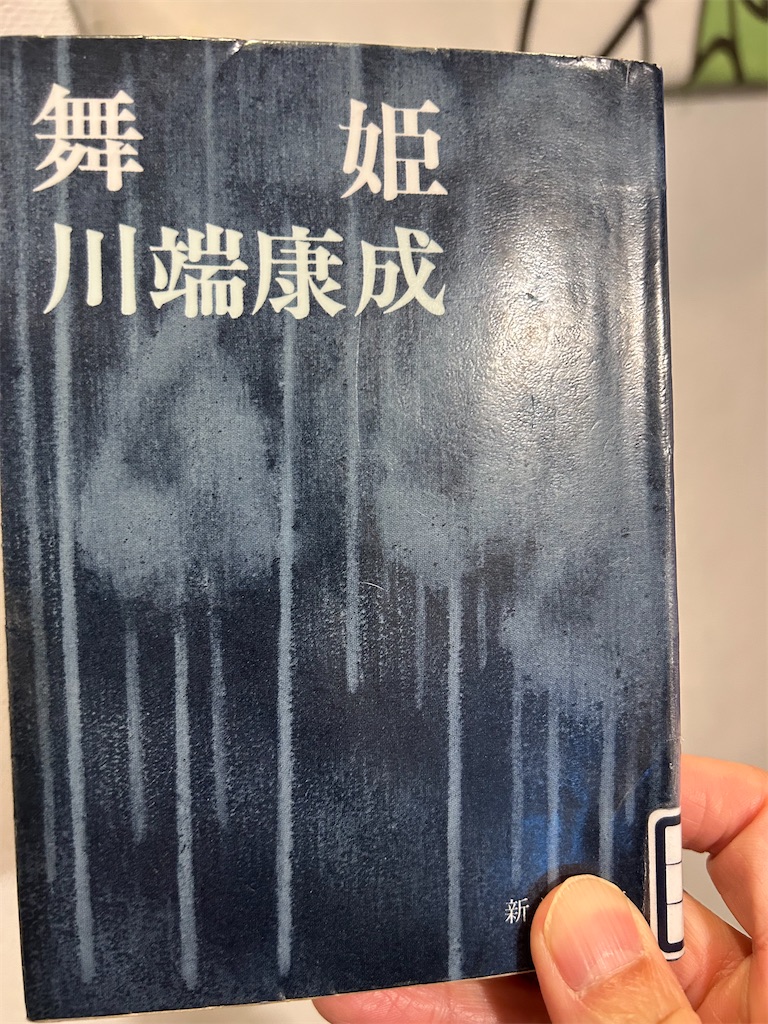
2、あらすじ
かつてバレリーナであった波子は、家庭がありながらも結婚前の元恋人である竹原と逢瀬を重ねていた。
夫である矢木も薄々気づいていながら、触れずにいた。
そんな矢木を父として慕う20歳の息子・高男、波子の夢を託された21歳の若く有望なバレリーナの品子の4人家族の間には常に緊張が孕まれていた。
国文学者の矢木だったが、名家だった波子の財産にたかり生活している有様。
アンバランスな家庭は、ある出来事をきっかけに崩壊の序曲を奏で始める・・・。
3、この作品に対する思い入れ、読んだキッカケ
『舞姫』といえば森鷗外ですが、川端康成も『舞姫』というタイトルで作品を書いています。
『伊豆の踊子』『雪国』『古都』などの傑作群から比べると地味さは否めませんが、バレリーナの母娘の話だったりして、なんか川端康成っぽいやんって思って読んでみました。
後期作品でキーワードとなる「魔界」という言葉が初めて出てきた作品であり、同時期の名作『山の音』の戦後の歪な家族関係にも通ずる作品でもあるのでとても興味深く拝読しました。
図書館で見かけて借りて、2025年末から2026年はじめにかけて年をまたいで読了したのも印象深い作品でした。
旅行先、実家でも読んでいたので、どことなく旅情と綯い交ぜになって不思議な感覚で読み進めました。
4、感想(ネタバレあり)
いや、まず触れねばならぬのは矢木一家のクセの強さ。
千鳥のノブもビックリです。
クセがスゴイ!!
ノーベル文学賞を受賞した文豪・川端康成の書評で、お笑い芸人のネタを被せてくる不謹慎な書評を書いているのは僕だけでしょうね(笑)
まあ、しかしクセ強めな一家ですよ。
母・波子はバレリーナで、40歳を過ぎても美しく、名家育ちのお嬢様で、現代流に言うとちょっとメンヘラ気質。
父・矢木は皮肉屋の穀潰しで、妻の資産で生活しながらそれでいて自分の金はせっせと貯め込んでいるどうしようもない愚物。
長女・品子はバレリーナとしては有望だけれど、師であり現在はバレエをやめて伊豆にいる香山を愛している。
長男・高男は若いのにシニカルなものの見方をして、家族、国家ですら信じられない寂しい人間。
こう考えると、品子が一番まともなように思いますが、物語の最期に突然香山に会いに行くために発作的に電車に飛び乗ってしまうような激しさを持っています。
父・スパイ、母・殺し屋、娘・超能力者のスパイファミリーもビックリなスパイラル(捻じれた)なファミリーですね。
お前ら何してんねん!!って、突っ込みながら読むだけでスルスル読めてしまう感じの登場人物たちのキャラクターと舞台設定が面白かったですね。
竹原と波子の結婚前の交際と、品子の香山への恋慕と慰問訪問の話など本来は核になりそうなエピソードが過去のものとして描かれているのが興味深かったですね。
現在が過去と常に呼応して描かれているのが、物語としての深みになっているように僕は感じました。
登場人物たちが感じているそれぞれの虚無感。
矢木家の4人が感じているような喪失感は何なのでしょうか?
かえって困難だった戦中のほうが、家族として助け合いながらまとまっていて、戦後に手に入れた自由を持て余すように関係が解けていくさまが、切なくもアイロニカルでした。
戦争が原因で堕落した修一が家庭を乱していく様が描かれていた『山の音』とは対照的な家族の描き方のように思います。
『舞姫』は家族を描いた物語であり、夫婦関係のねじれや奇異さを描いた作品でもあると思います。
70年以上昔に描かれた作品でありながら、夫婦間の愛の歪みや不実が描かれていて、さながら現代の希薄な夫婦関係、家族関係を描き予言したような作品でもあるかと思います。
「結婚はみんな、一つ一つ非凡のようですわ。・・・平凡な人が二人寄っても、結婚は非凡なものになりますのよ。」
夫以外の若い男を愛することで、かえって夫との関係性が良くなる妻(波子の友人)も描かれていて、自由であることで歪んでいく夫婦関係について描かれていたようにも感じました。
夫婦でいながら、家族でありがらも孤立していくという寂しさ。
「孤児根性」と自ら蔑んだような、川端康成の孤独な生い立ちが作品に反映されたのでしょうか。
さまざまに入り混じっていく人間関係ですが、僕としては『古都』のような女性同士のやり取りの場面なんかが好きです。
『舞姫』では、波子、品子、友子のやり取りですね。
とても感受性豊かに、それぞれの感情とかなしみが描かれていて、その心の動きに魅せられました。
かなしみ。
「悲しみ」でも、「哀しみ」でも、なく「かなしみ」と平仮名で表記されている川端康成の感じている「かなしみ」がとても情緒深く心の深いところに沁みていくようです。
日本古来の「もののあわれ」などの言葉に通ずるような、この国で大事にされてきた淡い心の移ろいを描くのがとても上手な作家だと思います。
崩壊していく家族の姿を現代的に描きながらも、3人の女性の間に描かれている古来からこの国に存在する「かなしみ」が描かれているのもアンビバレンツな感じで良かったです。
3人の女性はかなしい愛に生きています。
波子は妻がある元カレの竹原を愛してその妻に嫉妬し、品子はバレエを捨てて伊豆に籠った香山のことが忘れられず、友子は妻子ある男を愛してその男の妻が病弱なために彼の家族と子供たちを養うためにバレエを辞めてストリップ劇場で踊ることを決意する。
いやいや、どうしてそうなっちゃうんかなっていうぐらいに報われない愛に生きる3人の女たち。
穏やかで上品そうな外面に反して、心の内では炎が燃え盛っている。
何もかも焼き尽くすような恋情の激しさを感じました。
登場人物たちの中でも波子の心情がより仔細に描かれていて、恋人と一緒にいる時に白い鯉に見入ったり、「こわいわ」と急に恐怖の感情に囚われたりとつかみどころがありません。
韜晦としていて、どこか生命感を感じさせずに彷徨っているような、そんなつかみどころのなさがあります。
矢木も竹原もそんな波子のつかみどころのなさと、もの悲しさ、過剰なセンチメンタリズムを窘めながらも、強く惹かれて、結局は振り回されているようにも感じます。
バレエの演目で仏の演技をしてから一人の時に合掌をしたりしていて、どこか浮世離れしているようにも見えました。
結局、波子は竹原と添い遂げられたのか、家族は離散したのか結末は描かれませんでしたが、竹原との関係がどうあれ家族は崩壊していっていたように思います。
「魔界」という言葉は、矢木が所有する一休の書で書かれています。
「仏界、入り易く、魔界、入り難し。」
「仏界、入り難く、魔界、入り易し。」なら、悪に染まるのは簡単だが、悟りを開いて仏界に入るのは難しいみたいな意味でわかりやすいのですが、逆にすると難解で不気味に思えてきます。
品子は矢木にこの言葉の意味を問いますが、仏界は品子と波子の踊りのセンチメンタリズムのことだとか言って要領を得ません。
そもそも川端康成が『みづうみ』『眠れる美女』『片腕』などで描いた「魔界」とは何だったのか?
僕がこれらの作品から感じたのは、「取り返しがつかない過去の過ちに対する煩悶の末に変質する自我」であるように感じました。
地獄ではなくて、魔界。
地獄のほうがわかりやすいですが、なぜ地獄じゃなくて魔界なのでしょうか?
罪を犯したものが落ちて苦しむ世界というイメージが地獄ですが、魔界は自分自身も魔物になって入っていくおぞましい世界という印象があります。
魔物たちが跳梁跋扈する世界に入るために、自らも魔物になる。
一線を越えていく、人として超えてはならない何かを。
それが川端康成のイメージする魔界だったのではないかと僕は思います。
5、終わりに
ちょっと最後は「川端康成の魔界論」みたいになってしまいましたが、『舞姫』はすばらしい作品でした。
まだ語りつくせぬところもたくさんあるのですが、まあキリがないのでこのあたりでやめておきます。
やっぱ、川端康成ええなぁ。
とりあえず、新潮文庫版全読破してみたいですね。
↓ブログランキング参加中!!良かったらクリックよろしくお願いします!!