1、作品の概要
『みずうみ』は、川端康成の長編小説。
1955年4月15日に刊行された。
『新潮』1954年1月号~12月号に連載された。
文庫本で147ページ。
『女のみづうみ』というタイトルで映画化された。
女性のあとをつける男の暗い情念と幻想を描いた。
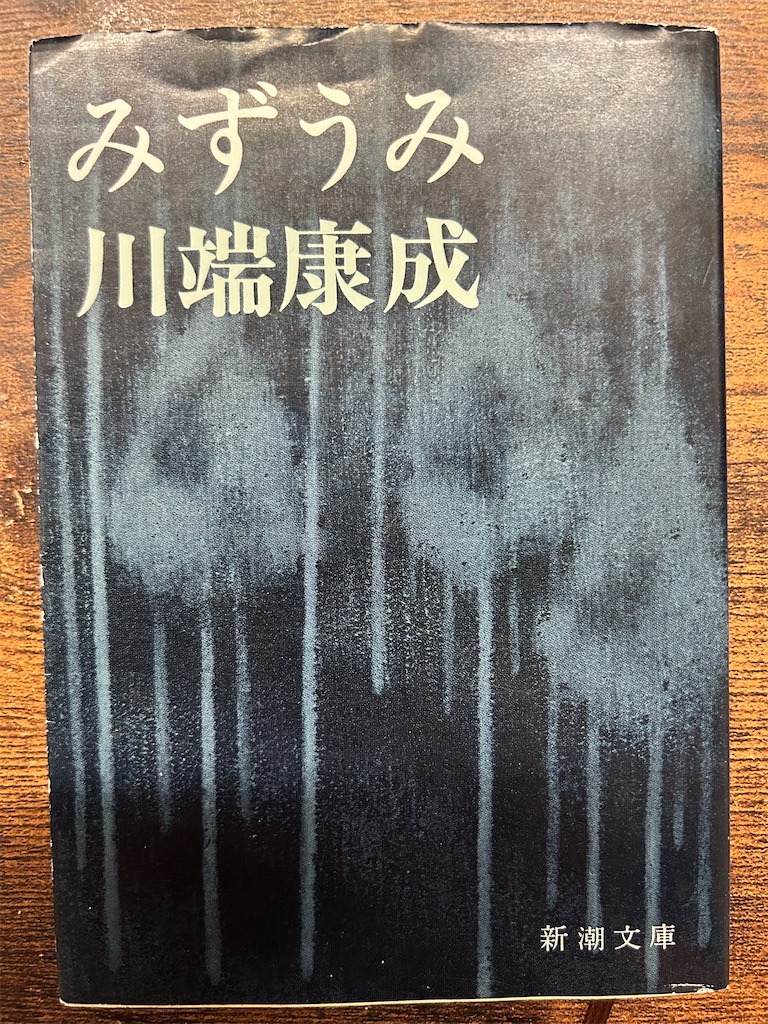
2、あらすじ
桃井銀平は、水木宮子の魔性的な魅力に惹かれてあとをつけて、狼狽した彼女から投げつけられたハンドバックの中から大金を手に入れて、東京から信州へと逃亡する。
銀平は軽井沢のトルコ風呂で、母方のいとこのやよいのこと、湖で変死した父親のこと、彼が高校教師だった時に交際していた少女・玉木久子について回想していた。
美しい久子との情愛、彼女との関係が露呈したことが原因で職を失った銀平だったが、別れた彼女に執着していた。
宮子は、有田老人の愛人になりもらった金で弟の啓助を大学に行かそうと目論んでいた。
啓助の友人の水野が交際している美しい少女・町枝の美しさの虜になり付きまとう銀平だったが、彼女には無視されて水野に突き飛ばされてしまう。
暗い情念を燃やし続ける銀平は一計を案じるが・・・。
3、この作品に対する思い入れ、読んだキッカケ
6~7年前ぐらいでしょうか、Xのやりとりでおすすめされて読みました。
川端康成といえば、『雪国』『伊豆の踊子』などの日本の美について語られる抒情的な作品が多いと思いますが、後期は「魔界」とも称される薄暗い作品群があると聞き、興味深く読みました。
主人公の銀平は、まんま中村文則の小説の主人公で出てきてもおかしくないほどのストーカー&歪んだ性癖の持ち主で、そんな作品が大好きなヒロ氏大喜びでした。
今回、ひさしぶりに再読してみました。
4、感想(ネタバレあり)
①魔界の妖しいきらめき、宮子と銀平
『みずうみ』は、3人称で銀平の視点の話に、水木宮子の視点の話が挟まって、また銀平の視点の話で終わる小説ですが、銀平の視点の話は現実に起こった出来事の上に、銀平の過去の思い出と、幻覚が重なって妖しくも幻想的な物語になっています。
裕福な家庭に生まれたお嬢さんだったのに、敗戦で財産を失い有田老人の愛人になって生計を立てている宮子。
25歳の美しい女性にしては不遇ともいうべき境遇で、おまけに初恋の人まで戦死しているのにどこかのびのびと生きているようにみえる宮子ですが、その美しさからよく男性にあとをつけられていて、銀平も彼女のあとをつけた男の1人でした。
よくあとをつけられる美女・宮子と、よく女性のあとをつける奇怪な男・銀平。
ずいぶんと奇妙な組み合わせの2人であります。
「同じ魔界の住人」というような表現もされていましたが、宮子もまた魔性をその身に宿した存在であったのでしょうか?
2人の直接の接点は、宮子が銀平につけられて、ハンドバックでぶん殴って逃げ出して、彼女の20万円入りのハンドバックを銀平が拾ったことですが、不思議と2人の接点は多く、数奇な運命の結びつきを感じさせられます。
20万円は現在でも大金ですが、当時の価値としてはいくらぐらいだったのでしょうか?
現在の200万円ぐらい?
有田老人の愛人になって、「若い血を吸わせて青春を犠牲にして」得た大金。
これが消失してしまったとしたら普通血眼になって探したりするものですが、宮子はあっさりあきらめて、むしろせいせいしたぐらいの感じを抱いたりしています。
いや、変な女ですね(笑)
手がじいんとしびれて、腕に伝わり、胸に伝わり、全身が激痛のような恍惚にしびれた。男にあとをつけられて来るあいだに身うちにもやついてこもっていたものが、一瞬に炎上したようだった、有田老人の蔭に埋もれた青春が一瞬に復活し、また復讐したような戦慄であった。してみると宮子にとっては、20万円をためる長い月日の劣等感がその一瞬に補填されたようなものだから、むだに失ったわけではなく、やはりそれだけ払う価いがあったのだろうか。
ほとんど全財産の20万円入りのハンドバックを投げつけて、恍惚に痺れている女。
うん、この人も変態ですね。
銀平の母の郷里の湖で、他殺も疑われるような変死を遂げた銀平の父と、美しい母。
2つ年上の従妹のやよいへの初恋と、同時に彼女を殺すことすら思い浮かぶような憎しみと劣等感。
教師時代に道ならぬ恋に落ちた久子。
久子よりも美しい15歳の少女・町枝。
いや、女おんな女ぁぁぁあって感じですね、銀平さん。
でも彼女らの魅力に総じて魔性魔力を感じて抗えないほどの強い引力を感じてします。
うん、あとをつけちゃってもしょうがないよね?
でも、単純に性的な欲求を越えた何かも感じてしまいます。
そうやって魅入られたように女性に惹きつけられて、幻想と記憶とともに生きているような、行きながら地獄に片足を突っ込んでいるような銀平の魔界。
彼の魔界は、川端康成自身の魂の暗闇でもあり、両親と死別したことで心の安寧を失い、その空白を埋めようと女性の美、肉体のパーツに憧憬し続けた倒錯にそのまま重なっていくように感じました。
(おそらく)死んだ、自分の(かもしれない)赤子の幻をみる場面も不気味すぎて魔界全開、メンタル全壊です。
こんなんがマジックリアリズム的に、現実と回想と一緒にぶち込まれてくるので背筋が冷たくなります。
銀平の這う地の裏側から、赤子が銀平につれて這っているのだ。鏡の上を這うのに似て、銀平は地の裏側の赤子と掌を合わせそうになった。冷たい死人の掌だ。
②銀平の歪み
銀平は、美しい母と、醜い父の間に生まれて、やがて2人とも死別してしまいます。
特に11歳の頃に起こった父のみずうみのほとりでの変死は、彼の精神に大きな歪みをもたらしたように思います。
精神的に孤児であること。
中村文則も、よく両親を亡くして歪みを抱えたまま成長してしまった人物を描きますが、川端康成自身も銀平の歪みに父の変死と、孤児となった心の空白を投影しているように思います。
川端康成の両親との死別による歪みは『少年』で詳細に語られていると思いますが、彼にとって創作する上での大きなテーマだったのでしょう。
有田老人も40歳以上年下の愛人に母を求めたように、銀平も女性に母性を求めているように思います。
冒頭の湯女とのやり取りの中に母性への異常な執着と神聖化がみられるような場面がありました。
銀平は真実涙ぐみそうになっていた。この湯女のの声に、清らかな幸福と温かい救済を感じていたのだった。永遠の女性の声か、慈悲の母の声なのだろうか。
トルコ風呂に行って、ひとまわり以上下の若い女性に対して慈母を感じるとか意味不明にもほどがありますね。
妄執極まれり、です。
従妹のやよいへの淡い初恋が、銀平の父の変死によって変質し、彼女に憎しみすら覚えざるをえないような状況になってしまったことも、銀平が女性に偏った関わり方をするようになった原因だったのかもしれません。
父の死によって、かつて親密だったやよいからも蔑みの視線を受けるようになってしまう。
また彼女が2つ年上だったこともあって、大人になって自分を置いて行ってしまったというような感情が銀平の中のみずうみの情景の中でずっとくすぶっていたのでしょう。
やよいと、みずうみでの情景は何度も繰り返し描かれます。
銀平は目をもっと高く暗い林の方に上げた。母の村のみずうみに遠くの岸の夜火事がうるっていた。銀平はその水にうつる夜の火へ誘われてゆくようだった。
とても暗い描写なのですが、蠱惑的な美しさを湛えた幻想的な情景・・・。
精神的な薄暗さ、トラウマ、妄執の狭間に妖しく輝く美しい光景が描かれています。
あの川端康成が書いているのですから、ただの気持ち悪い小説にはなりえず、はっとするような美しさが存在していますね。
③美への憧憬
銀平はなぜこのような奇行に走るのか?
女を付け回し、少女に心を惹かれて道を踏み外す。
孤児であることや、初恋の思わぬ形での失敗などもあるのかもしれませんが、美への憧憬もあったように思います。
女性のあとをつけることに関して、銀平はこのように言っています。
「(前略)なんて好ましい人だろう、人に道ですれちがったり、劇場で近くの席に坐り合わせたり、音楽界の会場を出る階段をならんでおりたり、そのまま別れるともう二度と一生見かけることも出来ないんだ。人生ってこんなものか。そういう時、僕は死ぬほどかなしくなって、ぼうっと気が遠くなってしまうんだ。この世の果てまで後をつけてゆきたいが、そうも出来ない。この世の果てまで後をつけるというと、その人を殺してしまうしかないんだからね。」
ここは、とても興味深いところだと思うのですが、銀平が女性の後をつけて行きつく感情は「かなしみ」なのです。
女性に対しての描写でこの「かなしみ」は何度が出てきます。
この少女の奇蹟のような色気が銀平をとらえてはなさなかった。赤井格子の降りかえしと白いズックの靴とのあいだに見える、少女の肌の色からだけでも、銀平は自分が死にたいほどの、また少女を殺したいほどの、かなしみが胸にせまった。
「悲しみ」や「哀しみ」じゃなくてひらがなで「かなしみ」というのも、意味深い気がしますね。
まあ、僕が綺麗なお姉さんの後をつけて警察にタイーホされたときに、上記の理由をいったところで変人扱いされること間違いなしでしょうがね。
女性の後をつけたりする銀平の異常行動と「かなしみ」はどこから生まれているのでしょうか?
それは自らが醜い容姿に生まれてきたということと、美への憧れと崇拝にあるのではないかと思います。
やたら猿のような足という描写がなされていますし、醜い父と美しい母というアンバランスな夫婦から生まれてきた生い立ち。
自らが手に入れることができない美に対して焦がれ、異常な執着を見せるのはそういった強い憧憬が根元にあるような気がします。
以前、川端康成が所蔵していたコレクションの展示が愛媛県美術館であったのですが、人体のパーツフェチだった彼が、ロダンの手の作品を何時間もずっと飽くことなく見続けていたというエピソードも記されていました。
美への憧れ、所有し眺め続けることで、安心感を得て一体となる。
ちょっと背筋が寒くなる思いもありましたが、川端康成の精神の一端に触れたように思い、それはそのまま銀平の異常行動の理由と美への憧憬へと繋がっていくように感じました。
まあ、ただの変態ですけどね(笑)
少女の黒い目は愛にうるんでかがやいていたのかと、銀平は気がついた。とつぜんのおどろきに頭がしびれて、少女の目が黒いみずうみのように思えて来た。その清らかな目のなかで泳ぎたい、その黒いみずうみに裸で泳ぎたいという、奇妙な憧憬と絶望とを銀平はいっしょに感じた。
美しい少女・町枝の黒い瞳がみずうみのようで、その清らかな目の中で裸で泳ぎたい・・・。
うん、重度の変態っすね。
ただ、銀平は決してその望みはかなわず(当たり前やろ)、彼女の美しさに触れることもできずに、自らの醜さを自認するという「憧憬と絶望」を感じます。
それが女性の美しさに触れた時に彼の心に去来する「かなしみ」ではないでしょうか?
そのかなしみは、みずうみに煌いた幻の稲妻のようにこの物語全体を貫き、妖しく照らしているように感じました。
5、終わりに
抒情的な作品が多く、日本的美と情景を卓越した文章で描写したノーベル文学賞作家・川端康成。
しかし、ちょいちょいフェチっぽいところもあるし、後期の「魔界」は彼の懊悩や強い憧憬を感じさせる、また違った側面からの文学的価値を感じさせられるような作品になっているかと思います。
『眠れる美女』もそのひとつですが、後期の狂気的な作品も含めて、川端康成の作品は興味深く、得難い光暉を放っているように思います。
↓ブログランキング参加中!!良かったらクリックよろしくお願いします!!