1、作品の概要
2009年10月に刊行された中村文則の長編小説。
短編集も合わせて、彼の8作目の作品。
天才スリ師の主人公が闇社会で巨大な力を持つ木崎に運命を翻弄されるサスペンス要素を盛り込んだ物語。
第4回大江健三郎賞受賞。
同作の英訳『The Thief』がウォール・ストリート・ジャーナル誌の2012年ベスト10小説に選ばれ、初めて海外で評価を受けた。
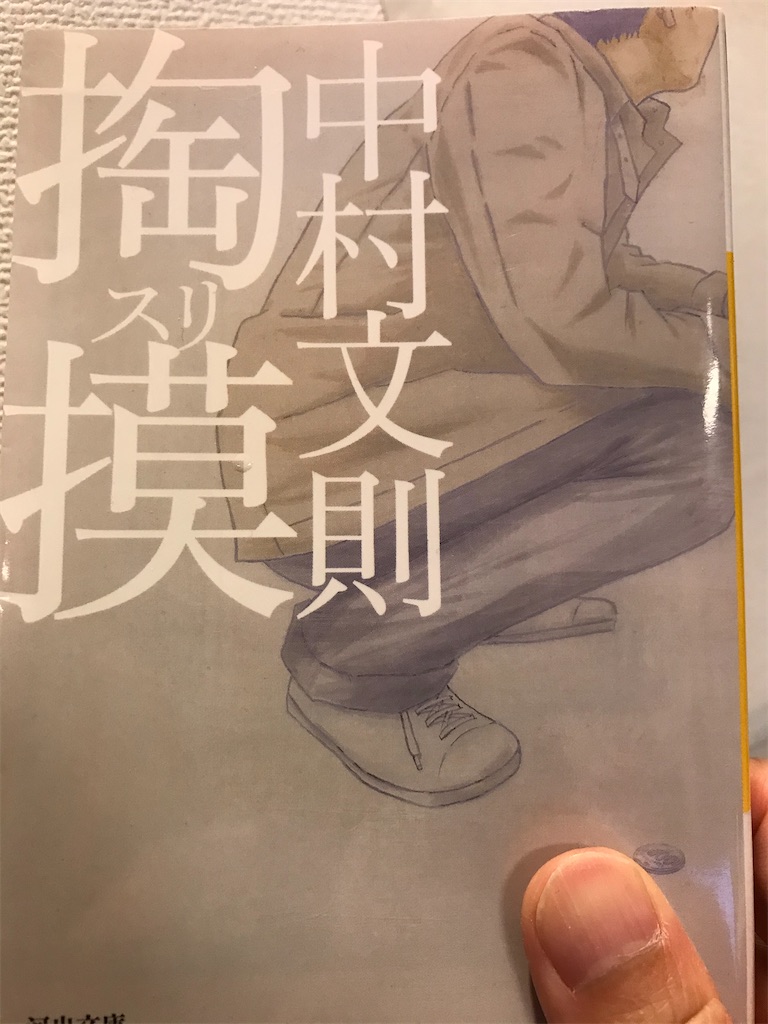
2、あらすじ
天才的なスリ師の西村は、スリ仲間の石川から誘われて木崎という闇社会で力を持つ男が計画した強盗殺人の犯罪に係わることになる。
石川は木崎によって消され、西村は東京を一旦離れるが東京に戻り一緒に強盗をした立花と再会。
再び、運命の歯車が回り始める。
ある日、スーパーでの万引き現場を目撃した母子と関わるようになり、男の子に金をやったりスリの手ほどきをするようになる。
疎ましく思いながらも、男の子のことをどこか自分の子供の頃のように重ねる西村。
木崎と再び邂逅し、3つのスリの仕事の依頼を受けた西村だったが・・・。
3、この作品に対する思い入れ
とても好きな作品だし、『銃』『掏摸』『悪と仮面のルール』でどんどん中村文則の作品にハマっていったように思います。
純文学的な要素を持ちながらも、とてもスリリングでページをめくる手が早くなるような作品ですね。
ただ「塔」の描写や、佐江子との破滅的な交わり、西村の破滅願望など純文学的な要素、複雑な内面の心理描写も並行して描かれています。
初めて読んだ時は、スリリングなサスペンス映画を観た時の感覚と、純文学的な作品を読んだ時の内に沈んでいくような感覚を同時に味わえて大変な驚きを感じました。
思えば、僕は『掏摸』を読んで決定的に中村文則の作品に耽溺するようになったのでしょう。
4、感想・書評
①純文学をアップデートする
唐突になんだかよくわからないテーマですが・・・。
僕は、中村文則が『掏摸』で純文学のアップデートを試みたように思うんですね(^^;;
大した読書家でもない僕が、こんな大層なテーマを書いたらガチ読書家の方から石を投げられそうですが。。
まぁ、どうかオッサンの戯言だと思って読み流してくださいませ(^^;;
まずは、純文学とは何かというところですが・・・。
純文学(じゅんぶんがく)は、大衆小説に対して「娯楽性」よりも「芸術性」に重きを置いている小説を総称する、日本文学における用語。
wikiとかにはこんな感じで載ってます。
僕の認識もこれとほぼ同じで、純文学とは娯楽性=ストーリーよりも芸術性=情景の美しさ、心理描写、人間の哲学・真理について書いたものだと思っています。
あとは、卓越した文章力と感性で、文章単体でも美しいと思えるもの。
娯楽性を排除した小説が面白いのか??
ってツッコミもあるかと思いますし、ぶっちゃけ純文学と称される作品のほうが読むのはシンドいし、ストーリーが平坦でわかりにく作品であることが多いかと思います。
中村文則の初期作4品なんかは正にそういった感じですし、『土の中の子供』は芥川賞に選ばれましたが、テーマも暗く先の読めないストーリーも、どんでん返しもありませんでした。
ただ、個人的にはそんなストーリーやキャラクター重視の作品より、いわゆる「純文学的」と言われる深みのある物語のほうが好きでした。
作品から受ける衝撃の深さ、大きさが捉えて離さず読後もずっと自分の生活や人生に入り込んでくるような濃密さがあったからです。
映画や、音楽も僕は同じ感覚で選んでいますが、どこまで自分の内部に深く食い込んで、どこまで遠くに連れて行ってくれるかが大事だと思っています。
個人的な感覚だし、別にそこまで求めなくてもいいんじゃ、って意見が大半なのだろうと思います。
でも、僕にとってはずっと大きなテーマで、だからこそ読む本、聴く音楽、観る映画、絵画にこだわるし、このスタンスは一生変わらないのだと思います。
僕は、『掏摸』を読んだ時に軽い混乱を覚えました。
スリや犯罪行為を主題として、スリリングな展開を楽しみながらも、主人公の複雑な心理描写や運命の不可思議さを説く・・・。
まるで、ハリウッド映画の娯楽性と純文学の深みが共存したような物語。
自分にとってはとても新しい感覚でした。
大げさかもしれませんが、僕は中村文則が『掏摸』を通じて純文学の現代版としてのアップロードを試みたのではないかと思っています。
ただでさえ本が売れなくなっている時代に、「ラノベ」なるポップな作品が幅を利かせてもはや純文学は死滅したかのうようなこの昨今。
純文学が生き残る術は娯楽性と芸術性のハイブリッドだったのではないでしょうか?
もちろん、そんないいとこどりの作品は誰にでも書けるわけはないのですが、中村文則はそれを成し遂げ、平野啓一郎の作品の軌跡にも同じような流れを感じることができます。
平野啓一郎の書評も書きたいのですが、この人の作品はなんだか覚悟がいりますね(笑)
40代の同世代の作家が躍進しているのを見るととても嬉しくなります。
②スリ、犯罪を描いた蠱惑的な作品
中村文則自身も、あとがきで「反社会的作品」と評しているようにこの物語は徹底して社会から外れた人間が描かれています。
北野武の映画じゃないけど、「全員、悪人」とかいうキャッチコピーでイケそうですね(笑)
西村がスリをする場面もとてもスリリングで息が詰まるような緊張感があります。
そのうち、藤原竜也とかが主演で映画化もしそうですね。
その入ってはいいけない領域の伸びた指、その指の先端の皮膚に走る、違和感だど消えうせる快楽を・・・
など、とても蠱惑的に他人の財布を盗む瞬間を描写しています。
中村文則が大学で犯罪心理学を学んだということもあるかと思いますが、犯罪と犯罪者の心理については作品中で繰り返し描かれます。
そして、登場してくる人間は、スリ仲間の石川、木崎、スーパーで出会った母子など犯罪者やどこかマトモじゃない人間たちばかりです。
道義的に正しいかどうかは別として、罪を犯す人間が繰り返し描かれていてそれぞれが抱える暗部が交錯して、黒い火花を散らします。
③悪、運命を司ろうとする木崎
『悪と仮面のルール』『教団X』『逃亡者』などでも繰り返し登場する悪を為す人間。
木崎は中村作品に初めて登場した明確な「悪」として描かれた存在で、木崎の存在が西村の運命を翻弄していきます。
中村文則が描く「悪」は、ただ犯罪を犯したり、他人を害したりするだけではなく、もっと複雑な側面を持っていて、得体が知れません。
木崎は全てに飽いているかのように見えて、突然上機嫌になったり、思いつきで行動してみたり不気味です。
そして、他人の人生に干渉することでまるで運命そのものであるかのように、人生に於いての何かの災厄であるかのように振る舞います。
気まぐれに他人の人生に入り込み、命を奪うことで快楽に震える。
圧倒的な力を持つ暴力そのもの悪そのもののような存在・・・。
いや、絶対関わり合いたくない種類の人間ですね!!
「・・・他人の人生を机の上で規定していく。他人の上にそうやって君臨することは、神に似てると思わんか。もし神がいるとしたら、この世界を最も味わっているのは神だ。俺は多くの他人の人生を動かしながら、時々、その人間と同化した気分になる。彼らが考え、感じたことが、自分の中に入ってくることがある。複数の人間の感情が、同時に侵入してくる状態だ。お前は味わったことがないからわからんだろう。あらゆる快楽の中で、これが最上のものだ。いいか、よく聞け」
圧倒的な力を背景に他人の運命を規定して飴玉のように口の中で転がしながらゆっくりと味わっていく・・・。
木崎と出会った人間は、そのように掌の上でころがされて弄ばれる。
単純に悪行を繰り返すというよりは、不吉な災厄そのもののような存在。
他人の運命に干渉して命すら奪い、国を揺るがすような事件を起こして、どんどん巨大な存在になっていきながらもそれにすら倦怠を感じて地獄を抱えている木崎。
東京で木崎と再会した西村の運命と命は、弄ばれ続けます。
巨大な悪から、運命からは逃れえないのでしょうか?
答えは西村がラストシーンで放ったコインに込めらているように思います。
④塔、破滅願望を抱える西村
天才スリ師である主人公の西村。
中村作品でよく出てくる登場人物のように複雑な事情を抱えて歪みを抱えたまま大人になっています。
おそらくは施設の出身で親の愛情を受けることができなかったような状況が推察されます。
もちろん、施設の出身で事情があって親から離れていても立派に育つ人間もいれば、裕福な家庭で親の愛情を受けて育っても歪んでしまう人間もいるとは思います。
ただ、彼の作品では施設出身で実の親から愛情を受けられなかった子供が、そのまま歪みを持ちながら成長してしまうというパターンが多く、西村も他人のモノを盗んでしまうという大きな歪みを持っています。
西村の歪みが複雑だったのは、子供の頃に何かに導かれるように盗んだモノをわざと落としたりして、その罪が明るみになるように振舞っていたことでしょう。
彼は何故盗んだモノをも落として自らの罪を明るみにしてあえて裁かれようとしていたのでしょうか?
それは、中村文則があとがきで書いていたように「光が目に入って仕方ないなら、それとは反対へ降りていけないい」と、西村が感じていたからでしょう。
自らの罪を明るみに出して裁かれることによって、光り輝く世界から遠い存在になっていく・・・。
自らを虐げるような、破壊するかのような仄くらい心のうちが見て取れます。
彼の行為を見咎めるように、いつも遠くにあり見下ろしていた「塔」。
実在のものではなくて、観念的なものだったのでしょうがおそらく道徳や倫理、人間としてこうあるべきといったような「立派で真っ当なもの」の象徴だったのでしょう。
そいういった「光」のような存在から自分は阻害されているという想い。
世界に背を向けて生きているという感覚・・・。
『遮光』を思い出しました。
あの時私は、太陽を睨めつけていた。太陽はちょうど水門の真上にあり、酷く明るく、私にその光を浴びせ続けていた。私はそれを、これ以上ないほど憎み、睨めつけていた。その美しい圧倒的な光は、私を惨めに感じさせた。この光が、今の私の現状を浮き彫りにし、ここにこういう子供がいると、世界に公表しているよな、そんな気がしたのだった。私はその光に照らし出されながら、自分を恥ずかしく思い、涙をこらえた。
強すぎる光は、暗がりで心地よく生きている人間には時に強すぎるし、中村文則自身も彼の小説の主人公もその光を避けるように生きています。
でも、決して前向きとは言えない生き方でも這いずるように暗がりの中で必死に生きている。
そんな姿がいつも胸をうちます。
そんな破滅願望を持ちながら、光に背を向けて生きている西村に身を寄せていた佐江子。
彼女もまた病んだ魂を抱えて、同じように薄暗い何かを持った西村にシンパシーを感じていたのでしょう。
「・・・私は目の前にある価値を、ダメにしたくなる。・・・何でだろう。何もいいことなんてないのに。自分が何をしようとしてるのか、わからなくなる・・・、あなたは、何か望みとかある?」
佐江子について書かれた場面は少ないですが、西村の心に深く食い込んだ存在であることが窺えます。
⑤魂を慰撫する緩やかな関わり、希望としてのコイン
登場人物が全員悪人と書きましたが、その上もれなく病んでますね(笑)
破滅と狂気の狭間であえぐように生きているように見えます。
他の作品では、わりとメンターのような存在(『土の中の子供』『何もかも憂鬱な夜に』の施設長、『逃亡者』のあの人)や、ドストエフスキー『罪と罰』におけるソーニャ(主人公の心を救う清らかな売春婦)のような存在(『遮光』のミキ)も見当たらずより行き止まり感が強いように思います。
ただ、この作品で西村の魂を慰撫するような存在はスーパーで出会った子供。だったのでしょう。
自分の境遇・幼いころの面影を重ねて何かと世話を焼き、子供にスリの手ほどきすらします。
唯一、心温まるような温かい交流の場面のように思います。
まぁ、スリの指南とかまともじゃないですが(笑)
まるで、自分の存在が消えてしまう前に何かを残したいと願うような、西村の魂の叫びにも思えてきます。
ある意味、主人公自身が誰かのメンターとしての存在になっていくという他の作品ではあまり見られない展開だと思います。
西村は子供に金をやったり、施設を紹介したりして最後に小さい箱を渡します。
まるでパンドラの匣のようにも思えるその箱は子供の希望に成り得たのでしょうか?
まるで自分が真っ当に生きられなかった埋め合わせをするかのように、自分の代わりに世界に対して真っ当に渡り合って欲しいと思うように想いを託して去っていきます。
ある種の継承。
連鎖する呪いからの脱却。
想いは伝わったのでしょうか?
ラストシーン、絶望の中で投げられる1枚のコイン。
中村文則が描く物語の最後に必ず提示される希望。
彼が投げたコインは希望となり得たのでしょうか?
5、終わりに
中村文則の作品が大きく変容して、多くの人に受け入れられるきっかけになった転換点のような作品だと思います。
初期のようなとことん内向的な作品が好きだという人の意見もとてもよくわかりますが、この作品以降ミステリー色の強い作品や、総合小説のような人生そのものを俯瞰するようなスケールの大きな作品を書いていると思うし、僕はこの作家はまだまだ進化していくと思っている。
僕自身は決して暗い性格ではないと思いますが、時々中村文則の文学が自分の暗部にそっと寄り添ってくれるように感じる。
生きづらさを感じることが多くても生きていこうって感じることができます。
『掏摸』は思い入れがある作品なので、書くのに勇気が要りましたが自分が感じていることは表現できたように思います。
読み返していて、以前気づかなかった物語が内包するメッセージにも気付かされたような気がしています。
